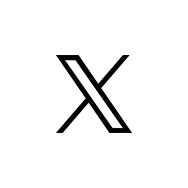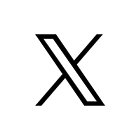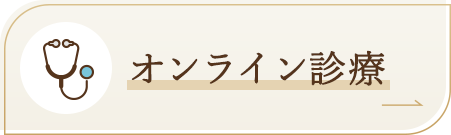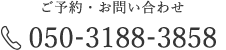- 半月板損傷とは?原因と種類
- 半月板損傷の症状チェックリスト
- 重症度別の治療法(軽度・中度・重度)
- 半月板損傷は治るのか?治療期間の目安
- リハビリ・筋トレは回復を早める?
- 放置するとどうなる?後遺症のリスク
半月板損傷とは?原因と種類
 半月板は膝関節の内側と外側に存在する軟骨組織で、衝撃を吸収し関節の動きをスムーズにする役割を担っています。ここに亀裂や断裂が起こった状態を「半月板損傷」と呼びます。スポーツや事故で急に膝に強い力が加わったときに生じることが多く、特にサッカーやバスケットボールなど方向転換の多い競技ではよく見られます。
半月板は膝関節の内側と外側に存在する軟骨組織で、衝撃を吸収し関節の動きをスムーズにする役割を担っています。ここに亀裂や断裂が起こった状態を「半月板損傷」と呼びます。スポーツや事故で急に膝に強い力が加わったときに生じることが多く、特にサッカーやバスケットボールなど方向転換の多い競技ではよく見られます。
一方で、加齢によって半月板がもろくなり、ちょっとした動作でも損傷する「変性型半月板損傷」もあります。立ち上がった拍子や階段の昇り降りで痛みが出る場合には、年齢による変化が関係していることが少なくありません。
半月板損傷の症状チェックリスト
半月板が損傷すると、膝の動きにさまざまな支障が出てきます。初期は「なんとなく違和感がある」程度でも、次第に膝が腫れてきたり、動かすと引っかかるような感覚が現れたりします。典型的な症状を下にまとめました。
症状の特徴
- 膝の腫れや熱感:関節内に炎症が起こり、触れると熱を帯びている
- 動作時のひっかかり:膝を曲げ伸ばしすると何かが邪魔をするように感じる
- 可動域の制限:痛みや腫れで膝がしっかり伸びない、深く曲げられない
- 関節液の貯留:いわゆる「水がたまる」状態で膝が重く動きにくい
- 歩行時の痛み:立ち上がりや歩き出しの際に鋭い痛みを感じる
- ロッキング現象:膝が突然動かなくなり、強い痛みとともに固まってしまう
これらの症状が長引く場合、自然に良くなることは少ないため、整形外科での診断をおすすめします。
重症度別の治療法(軽度・中度・重度)
軽度の損傷
軽い痛みや腫れのみで日常生活には大きな支障がないケースです。この場合は安静と冷却、湿布や消炎鎮痛薬による保存療法が中心となります。
症状が落ち着いたらリハビリを開始し、大腿四頭筋やハムストリングスといった膝周囲の筋肉を鍛えていきます。筋力を高めることで関節の安定性が増し、再発防止にもつながります。
中度の損傷
膝に引っかかり感や不安定さがあり、運動や長時間の歩行で痛みが強まる状態です。リハビリや物理療法を継続的に行い、必要に応じてサポーターを使用して膝を安定させます。保存療法で改善が見込めることも多いですが、症状が長引く場合には手術が検討されることもあります。
重度の損傷
膝がロックされる、強い腫れが引かない、歩行すら難しい場合は重度の損傷が考えられます。こうしたケースでは関節鏡を用いた半月板の修復術や部分切除術が行われることがあります。手術後は必ずリハビリを行い、関節の柔軟性と筋力を回復させることが重要です。
半月板損傷は治るのか?治療期間の目安
 半月板損傷の回復期間は損傷の程度と治療方法によって大きく変わります。保存療法で改善する軽度のケースでは、数週間から2〜3か月程度で日常生活に支障なく過ごせるようになります。
半月板損傷の回復期間は損傷の程度と治療方法によって大きく変わります。保存療法で改善する軽度のケースでは、数週間から2〜3か月程度で日常生活に支障なく過ごせるようになります。
一方、手術が必要な場合にはさらに長期のリハビリが必要です。部分切除術ではおよそ2〜3か月で復帰できることが多いですが、縫合術では半月板の癒合を待つため5〜6か月程度を要するケースもあります。スポーツ競技への本格的な復帰は、医師の判断を仰ぎながら段階的に行うことが重要です。
リハビリ・筋トレは回復を早める?
 筋力トレーニングは半月板損傷からの回復を助ける重要な要素です。大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えることで膝関節が安定し、損傷部にかかる負担を分散させることができます。さらに筋肉がつくことで歩行や階段の昇り降りといった日常動作が楽になり、リハビリ自体の効果も高まりやすくなります。
筋力トレーニングは半月板損傷からの回復を助ける重要な要素です。大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えることで膝関節が安定し、損傷部にかかる負担を分散させることができます。さらに筋肉がつくことで歩行や階段の昇り降りといった日常動作が楽になり、リハビリ自体の効果も高まりやすくなります。
ただし、炎症が強い時期に無理に運動をすると悪化する可能性があるため、トレーニングは必ず主治医や理学療法士の指導のもとで行うことが大切です。
当院では、リハビリ専用の施設を完備し、経験豊富な理学療法士が患者さま一人ひとりの症状や回復段階に合わせたプログラムを提供しています。そのため、安心して適切なリハビリを受けていただける環境が整っています。
まとめ
半月板損傷は軽度であれば保存療法で改善することもありますが、中度から重度になると手術や長期のリハビリが必要になることもあります。
治療期間は症状や方法によって数週間から半年以上と幅があります。大切なのは「無理をせず、適切な診断と治療を受けること」です。膝の違和感や痛みを感じたら早めに専門医へ相談し、再発や後遺症を防ぎましょう。